はじめに
本記事はCFP試験整理用として、2024第1回・問10D (非上場株式の評価:株主区分の判定)をまとめたものです。
試験を通じて同族株主・筆頭株主グループ・自己株式の扱いを整理し、最後にポイントを総復習します。📝
本文の前提(要点)
- 同族株主は、原則「株主1人+同族関係者」の議決権合計が30%以上となるグループ。🧩
- 同族関係者には個人だけでなく法人(特殊の関係のある法人)も含まれる。🏢
- 筆頭株主グループが50%超を握ると、他グループは同族株主に該当しない。📈
- 自己株式は議決権なし。議決権総数の算定から除外(会社法308条2項・財産評価基本通達188-3イメージ)。⚙️
- 相続放棄の有無は、株主区分の判定そのものには原則影響しない。📌
結論
最も適切なのは 選択肢2 です。🎯
各選択肢の解説
❌ 不適切(選択肢1)
「同族関係者に法人は含まれない」は誤り。
同族株主は株主1人+その同族関係者で構成され、同族関係者には個人に限らず、特殊の関係のある法人も含まれます。
→ よって「法人は含まれない」という断定が×。💥
⭕ 正しい(選択肢2)
筆頭株主グループが議決権総数の50%超を保有していれば、他の株主グループは同族株主には該当しません。
支配グループが過半を押さえているため、別グループは同族株主グループを形成しない、という整理でOK。✅
❌ 不適切(選択肢3)
相続放棄の有無は、株主区分(同族株主かどうか)の判定に原則関係なし。
特定遺贈で株式を取得すれば、その者の実際の議決権割合に基づき判定されます。
「放棄していれば同族株主にならない」というのは言い過ぎで×。⚠️
❌ 不適切(選択肢4)
自己株式は議決権を有しません(会社法308条2項)。
したがって、株主区分で使う議決権総数の算定でも、自己株式はカウントしないのが原則(財産評価基本通達188-3の考え方)。
「自己株式も議決権ありとして計算」は×。🛑
ポイント

- 同族株主=「1人+同族関係者」で30%以上。法人も含むことに注意。🏢
- 筆頭株主グループが50%超なら、他グループは同族株主にならない。📊
- 相続放棄の有無は無関係。判定はあくまで議決権割合で。🧮
- 自己株式は議決権ゼロ→議決権総数に含めない。⚙️
- 株主区分は評価方式の分岐(原則方式/配当還元)に直結。📚
出典元
日本FP協会「CFP資格審査試験 過去問題」
https://www.jafp.or.jp/aim/cfp/cfp_exam/mohan.shtml
※本記事はCFP試験整理用として過去問題をまとめたものです。
実務や最新の税法適用を保証するものではありません。実際の相続や税務については、必ず最新の法令や公的資料をご確認ください。
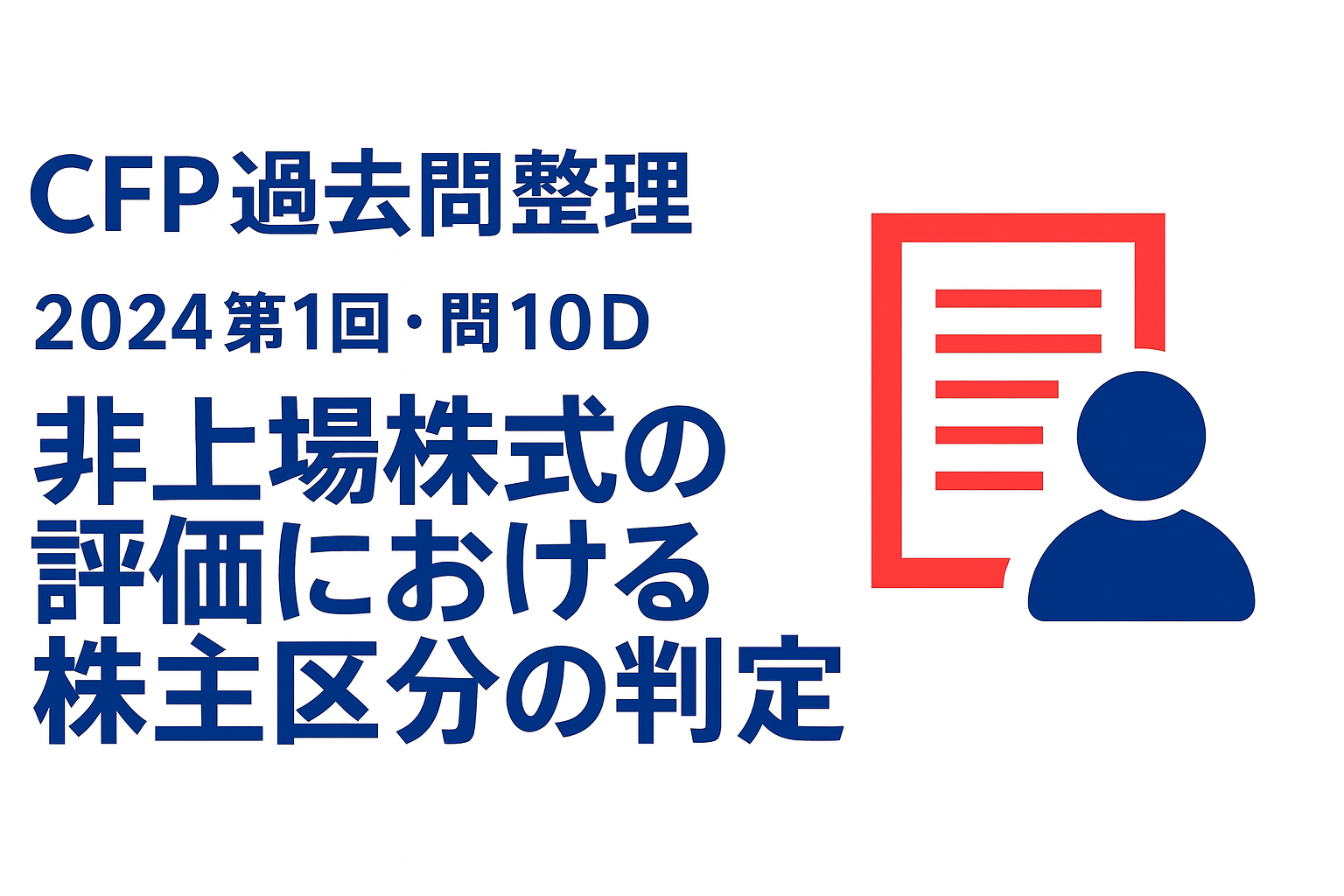
コメント