はじめに
本記事は CFP試験整理用 として、2024第1回・問2B (遺言の法律上の効力) をまとめたものです。
試験問題を通じて「遺言で定められる効力範囲」の基本を整理し、最後にポイントをまとめます。
本文の前提(要点)
- 遺言は相続分の指定・遺産分割方法の指定・信託の設定などに効力を持つ。📜
- 祭祀主宰者の指定も可能であり、子がいる場合でも有効。👪
- 一方、法律で認められない遺言内容は効力なしになる。⚠️
- 予備的遺言(先に死亡した場合に孫へ相続させる等)も有効。✅
結論
最も適切なのは 選択肢1 です。🎯
各選択肢の解説
⭕ 適切(選択肢1)
民法908条により、被相続人は遺産分割方法を定めたり、第三者に委託することも可能。
したがって法的効力あり。
❌ 不適切(選択肢2)
民法1088条により、遺言による信託設定は認められている。
「効力がない」とするのは誤り。
❌ 不適切(選択肢3)
祭祀主宰者の指定は民法897条で有効と規定。
相続人に子がいても効力は否定されない。
❌ 不適切(選択肢4)
孫への承継を定める「予備的遺言」は有効。
「効力がない」とするのは誤り。
ポイント

💡 ポイントまとめます
- 遺産分割方法の指定や委託は有効(民法908条)。
- 信託設定の遺言も可能(民法1088条)。
- 祭祀主宰者の指定は子がいても有効(民法897条)。
- 予備的遺言(孫への承継指定)も効力あり。
出典元
日本FP協会「CFP資格審査試験 過去問題」
https://www.jafp.or.jp/aim/cfp/cfp_exam/mohan.shtml
※本記事はCFP試験整理用として過去問題をまとめたものです。
実務や最新の法令適用を保証するものではありません。実際の相続や税務については、必ず最新の法令や公的資料をご確認ください。
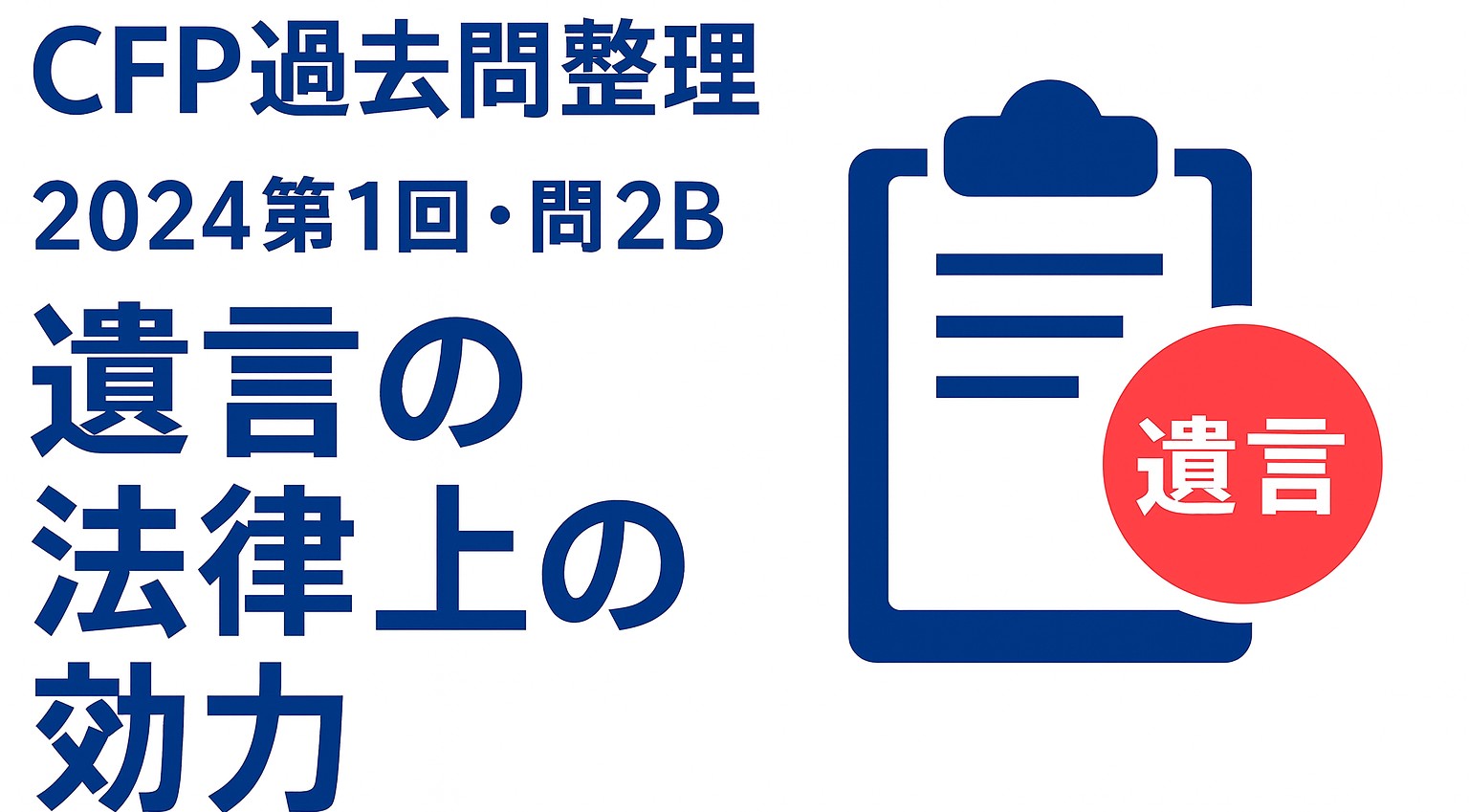
コメント